

上毛かるた(財団法人群馬文化協会発行)の謎を解く・・・・
2001年9月26日開始
|
ことの起こりは、2001年9月5日のチャットルームで「「上毛かるた」の想い出」をテーマに論議が盛り上がりました.「市町村大会の思い出」や、「「よ」の絵札」談義、「「ち」の読み札は、何十万人が一番少ないのか?」「太田の日系ブラジル人の方に大会に出ていただいて、第1回上毛かるたワールドカップ(JOMOカップ)をやったらどうか?」というような、どーでもいーような話題ばかりだったのですが、参加していた「クマぷぅ@桐生市」氏から以下の疑問が投げかけられました. |
| 「どうして「い」と「ら」の読み札だけがピンク地なのか?」 |
そこで、チャットの終了時より、氏は裁断のあまく、隣の絵札の模様まで写っている昭和51年当時の「上毛かるた」を元に、上毛かるたの製作過程の推察が図られました.氏の深遠な考察は群馬県民としては感涙に咽ぶものであります.上毛かるた関連サイトは数あれど、ここまでディープなのものはないでしょう.以下は氏が、「医療人のための群馬弁講座」ファンの皆様にいただいた特別寄稿です.(一部、管理人鈴木が読みやすいように整形しています.) |
![]()
| 「上毛かるた」(昭和51年版)の絵札は 以下のように一枚になっているものと推定されます。 (左の「い」、「ら」はピンクの読み札) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断片的にいろは順で並んでいますが、 それ以外の部分の整合性がいまいちです。 似たような柄目のものがありますので、 並べ間違いかと確認しましたが、 同系色の札同士でも入れ替えられるような部分はありません。 特に不思議なのが、 1行目と3行目のつながり具合でしょうか? いろはにほへとちりぬるわ(?)、 「わ」ってなんぢゃ?って感じですね。 しかし、2行目の「お」は完全に1行目の「ほ」と繋がっています。 なにしろ、「お」に描かれている鳥の羽が「ほ」の下部にはっきりと見えますの で…、 さらに言いますと、 1・2行目の左端には、単色のピンク色が見えます。 おそらくは、読み札の「い」と「ら」がここに繋がっているのではないでしょうか? そう考えますと、昭和51年当時の再々改訂版では、 1枚の版で印刷されている可能性まで見えてきます。 ピンクの読み札は「い」と「ら」、それに予備の「い」と「ら」と、 文字の入ってないピンクの読み札2枚の計6枚が入ってますので、 そこまでが1枚の版であるならば、 総てが1枚の版で作られている可能性のが高いのではないでしょうか? ピンクのもの以外の読み札を別の版で作ったなら、 あえてそこにピンクを入れて、 2色刷りにする意味合いが薄くなるようにも感じます。 版代が単色と2色では結構差がありますしね。 ピンクの予備札は4枚が裁断されないで2×2の大きさのまま封入されております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なんと深い考察!! チャットしていた「いわちゃん@太田市」氏からは裁断法による推定が行われました. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷が済んだシートを裁断するのに、直線カットのみの裁断機をつかい手作業で1列ずつカットしているのか、シートを一度に44枚のカードに打ち抜いて居るのかが問題なのですが、たぶん後者だと思います。もしそうだとすると、カッターも特注になるので、これもコストの問題から、絵札と読み札で別々のカッターを使っていることは考えにくく、そうすると絵札の方でも2×2のカットをしている札が存在する事になります。おそらくこれが白札なのでしょう。そうすると、8×4プラス6×2と言った並び方になるのではないかという推測が立ちます。僕の持っている札では縦の位置関係が殆ど判らないので、最後はクマぷぅさんに頼ってしまうのですが...。おそらくカット済みの白札は、2×2を直線の裁断機で手作業で切っているのでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「8×4プラス6×2」で、印刷しているとすると、クマぷぅ氏の推定とは版の形は変わってしまいます.これを踏まえてクマぷぅ氏はさらに検討を重ねてくれました. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もしかしたら、印刷時期によって、版の形状が違うのかもしれません。なぜなら、私が所有する版の絵札は一部並べた順番が間違っている可能性はあるものの、縦方向の繋ぎはだいたい合っているからです。ここで、それぞれが持っている版の製版形式が違うとしたならば、議論自体が不毛である可能性まで出てきてしまいますけどね(苦笑)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と続けています.謎はまた深まっていきますね・・・・ 「ピンクの2x2」札がこれを解くカギのようですが・・・・ どうして「い」の下は「ら」で、それがピンク地になった理由は・・・・何なのでしょう??ほんとうに「上毛かるた」は版ごとに印刷方法が変わっているのでしょうか? |
![]()
「どうして「い」と「ら」の読み札だけがピンク地なのか?」
2002年12月26日追記
| 上毛かるたの裁断の謎は、一応の解明をみたものの、「ピンク地」の謎は解明されていませんでした.この段をお読みになった倉渕村権田の東善寺・村上泰賢和尚様からメールをいただきました.東善寺は、最近再評価されている郷土の偉人・小栗上野介の菩提寺でもあります. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【和尚様のメールより転載】 上毛カルタの「い」と「ら」についてご報告します。 今年6月に「上毛かるた」の作者浦野匡彦氏の娘西片恭子さんの著『上毛かるたのこころ』が、中央公論事業出版から発行されまして、その中に「い」と「ら」が赤くなっている詳しい経過が書かれています。 『上毛かるたのこころ』P128より引用します。(註:太線は編集者:すずき@東毛によるものです) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「前述したように小栗上野介にこだわり続けて発禁となることを恐れた父は、小栗公を引っ込め高山彦九郎・国定忠次等と共に詠み込めなかったこれ等の人々を「雷と空っ風上州名物」と応募した詞を「義理人情」という上州人気質の表現で使って表すことにした。 しかし、それでも物足りず、何とかこれらの人々を強調したいと願う思いが、最後の段階で箱詰めの順序に思いついたという。 現在でも箱を開くと一番上に「い」と「ら」がある。いろは順でゆくと「ら」は中に入ってしまうが、これを入れ替えて初版からこの順序を採り、いろはがるたの「い」を一番上に置き「ら」を並べてこの二枚の札のみ赤く染め目立たせたのであった。 これは、父達がかるたに詠めなかった人々をいつの日か語らなければの思いを表現して、「ら」行の順列に上毛三山と浅間山を配して、彼等が山々そびえる上毛野地で活躍した人々であるという意図まで強調した。」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と、あります。 敗戦下、すべての出版物をGHQ(占領軍司令部)によって検閲されていたことを背景にしての話です。 この本で、小栗上野介は明治政府によって逆賊扱いされ、敗戦後はGHQによって軍港都市横須賀の恩人だから軍国主義者とされ、二重の汚名を着せられていたことがわかります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では、上のクマぷぅさんの結果と照らし合わせてみましょう.「い」と「ら」はピンク地、そして薄いピンクの札は、いまでもおそらく「ら」の札の下に封入されているであろう札です.上毛三山と浅間山の札は「藍色の太字」にしてみます. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どうです?浦野匡彦氏の気持ちが見事に込められているではないでしょうか?私たちには奇異に感じたこの配列にもこんな気持ちが込められているなんて・・・・(2003年版で、この配列になっていることを確認しました.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上毛カルタは50年以上に渡って群馬人に愛されているアイテムではありますが、敗戦後の微妙な時代に生まれてしまったために、小栗上野介をはじめ、北海道でも九州でも知られている(ある意味では一番群馬人としての知名度の高い)国定忠治、(戦後の歴史教科書では表舞台から去った)高山彦九郎などの郷土の偉人を始め、カルタの完成後に全国的にも有名になった群馬交響楽団や岩宿遺跡なども詠まれていないのです.ぜひ今世紀には、新たに読み札を刷新してみてはいかがでしょう?カルタも決して不可侵のものでもないでしょうから・・・ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上毛カルタをはじめ、カルタ文化は群馬県に深く浸透し、群馬県は、郷土カルタ(「○○カルタ」など)の普及率が全国一位だそうです.でも日本人の教養として、百人一首もいかがでしょう?群馬の子供は百人一首を「ぼうずめくり」にしか使っていないのもなんだかねぇ(笑) |
![]()
|
■2003年版では「た:滝は吹き割れ、片品渓谷」ですが、以前は「「た:滝は吹き割り、片品渓谷」でしたよね.現在地元では「吹き割れの滝」に統一しているので、地元の意向を反映したものと思われます.(TBSラジオの永六輔氏の番組に地元の利根村観光局がスポンサーになっているのですが、この中でも「ふきわれ」と言っているのを確認しました.) いつから、「り」→「れ」になったのでしょうか? |
| ■2003年版では「く」の読み札は、「草津(くさづ)よいとこの温泉(いでゆ)」ですが、草津の読みは「くさづ」になっていて、地元読みの「くさつ」とは異なっています.その後、三束雨@藤岡さんが、県立図書館で調べたところ、当初発行された時は「くさず」だったようです.いつから「くさづ」にかわり、地元の地名表記は「くさつ」になったのか?「ザスパ草津」ももはや全国区.地元の群馬内ですら、かの有名な温泉地の地名表記が違うというのも何かおかしい気がするのですが・・・東毛では「くさづ」と言ってますし、
地元でも「くさづ」と言っているようなんですが・・・・・※上毛カルタ初版は一見の価値あり!三束雨@藤岡さんのブログで!こっちみてくんなぃ! |
| 皆様のお持ちの「上毛かるた」、今一度お手持ちの絵札を、読み札を確かめてみてください.幼き頃、熱い思いで見つづけた絵札に新たな発見があるに違いありません. この件についてのご意見・新発見などございましたら、ぜひ 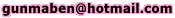 までメールを下さい.または掲示板「どーなん?そーなん?」に書き込まれることも大歓迎いたします. までメールを下さい.または掲示板「どーなん?そーなん?」に書き込まれることも大歓迎いたします. |
| ご寄稿いただいた「クマぷぅ@桐生市」氏、裁断についての意見をお寄せくださいました「いわちゃん@太田市」氏、「い」と「ら」の謎をご教示くださいました東善寺・村上泰賢和尚様に改めて厚く御礼申し上げます. |