|
私は東毛地区出身で、「めかいご」と呼んでいました.(「目蚕」なのかな?とずっと思っていました.)
このページを作るためにいろいろ方言を収集していくと、高崎以西と、利根・多野郡(吉井町除く)区では「めかいご」といわないことがわかりました.
わずか数10kmの範囲で、病気の呼び名が変わることを発見したのはびっくりです!
1998年、当講座を開設した当時、概ね下のような分布想像図を考えてみました.でも郡部に関しては、情報が少なかったので、私の推定が多分に含まれています.
▲1998年当時私が考えた分布想像図
註:当時は、館林邑楽地区の
「めけご」の存在については
気づいていなかった.
|
めかいご
図の淡橙色 |
中〜東毛地区(少なくとも桐生、太田、前橋では用いられている)
足利市でも用いられている.伊勢崎の一部では「めかいこ」と濁らない.
利根川以東の平野部
|
めかご
図の橙色 |
吾妻、沼田、利根地区、勢多西北部
藤岡、神流川流域の多野地区(なぜか離れているのだが・・)
なんと、長野県小諸市、栃木県上都賀郡足尾町でも!
もともとはこの言葉が語源で、「めかいご」がその転訛なのでは?? |
めっぱ
図の黄色 |
高崎以西(烏川・碓氷川・鏑川沿い;高崎、安中、渋川、甘楽地区)
;ほぼ高崎の文化圏に一致した分布を示す.
アクセントは、めっぱ.
やや尻上がりに発音. |
|
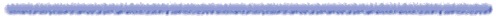
その後の経緯
さらにこの件を掘り下げていきます・・・・ (考察は当時のものです.)
 私の元上司の、小諸市某クリニック院長T先生より、長野県小諸市(かつて元JR信越線で群馬と直結)の情報が寄せられました. なんと!小諸では「めかご」と呼ばれているそうです!長野東信地区でも「めかご」とは! 私の元上司の、小諸市某クリニック院長T先生より、長野県小諸市(かつて元JR信越線で群馬と直結)の情報が寄せられました. なんと!小諸では「めかご」と呼ばれているそうです!長野東信地区でも「めかご」とは!
うーん、今までは「鉄道が方言分布に大きな影響を及ぼす.」と考えていた私の仮説が大きく覆りました.当然「めっぱ」圏と考えていたのですが・・・・ 碓井郡松井田町(JR信越線沿い)の友人をもつ群馬大学付属病院川野先生によると、「松井田は「めっぱ」圏でしたよ.」との情報だったのですが・・・・
この「めっぱ」というのは、正確にはどのように分布しているのでしょうか?私の予想では、高崎文化圏のみの分布なのですが、この2つの単語の境界線はどこなのか?
 「こうで」のページにも書きましたが、実家(太田市)にある「太田市史」を読んでみました.(1999.1.5) 「こうで」のページにも書きましたが、実家(太田市)にある「太田市史」を読んでみました.(1999.1.5)
すると、ありました!「民俗・医療」の項に「めかご」!!(ちなみに「めかいご」の項はない.)すなわちこれから推定されることは、やはりもともとは「めかご」であって、「めかいご」はその転訛ではないか?ということです.
しかも「太田市史」には民間伝承による治療法として、「籠を、半分井戸にみせるとなおる」「他人にうつすとなおる」などと、大胆なことが書いてありました.すごいですねぇ.この手の本も楽しめますよね.うーん、でも謎は深まるばかり・・・・
 桐生市の病院で、新たな情報を入手しました. (1999.1.24) 桐生市の病院で、新たな情報を入手しました. (1999.1.24)
栃木県上都賀郡足尾町でも「めかご」と言っていた!そうです.足尾町は、昔は足尾線(現;わたらせ渓谷鉄道)で、桐生市と結ばれています.栃木といっても、実質的には群馬の文化圏ともいえましょう.桐生では「めかいご」といわれています.わたらせ渓谷鉄道の沿線は、桐生市、山田郡大間々町、勢多郡黒保根村、勢多郡東村、そして上都賀郡足尾町.
どこで、「めかご」が「めかいご」に変化するのか??
 群馬県消防学校で、講義をした際に、余談で分布図を描いて、県下から集まっている消防士の方々の意見を伺ったところ、やはり概ね上の分布図のようでいいのではないか?ということになりました.推察が当たっていて、うれしかったです.甘楽地区も、「めっぱ」圏であること、吾妻、多野、利根地区は「めかご」圏であることが確認できました.第9期救急II過程のみなさん、ご協力ありがとうございました.(1999.2.12) 群馬県消防学校で、講義をした際に、余談で分布図を描いて、県下から集まっている消防士の方々の意見を伺ったところ、やはり概ね上の分布図のようでいいのではないか?ということになりました.推察が当たっていて、うれしかったです.甘楽地区も、「めっぱ」圏であること、吾妻、多野、利根地区は「めかご」圏であることが確認できました.第9期救急II過程のみなさん、ご協力ありがとうございました.(1999.2.12)
 勢多郡東村の学生に聞くと、「めかいご」とのこと.やっぱり県境で言葉も変わるのかな?(1994.4.14) 勢多郡東村の学生に聞くと、「めかいご」とのこと.やっぱり県境で言葉も変わるのかな?(1994.4.14)
 この分布などを考慮し、「群馬県の言語文化に関する一考察」のページを大幅改定しました.「めっぱ」は、高崎の文化というよりは「烏川・碓氷川・鏑川流域」の文化なのかも?多野郡でもこの流域の吉井町は「めっぱ」だし.(1999.6.28) この分布などを考慮し、「群馬県の言語文化に関する一考察」のページを大幅改定しました.「めっぱ」は、高崎の文化というよりは「烏川・碓氷川・鏑川流域」の文化なのかも?多野郡でもこの流域の吉井町は「めっぱ」だし.(1999.6.28)
 群馬大学で玉村町出身の方とこの件について話したら、「玉村町では、町の西の方では「めっぱ」、東の方では「めかいご」と呼んでいると思う.私は西の方で「めっぱ」と呼んでいたのだけど、東の方に住む友人が「めかいご」といったので驚いたのを覚えている」との話!玉村町がこの文化の緩衝地帯!?(2000.10.12) 群馬大学で玉村町出身の方とこの件について話したら、「玉村町では、町の西の方では「めっぱ」、東の方では「めかいご」と呼んでいると思う.私は西の方で「めっぱ」と呼んでいたのだけど、東の方に住む友人が「めかいご」といったので驚いたのを覚えている」との話!玉村町がこの文化の緩衝地帯!?(2000.10.12)
と謎は深まるばかり・・・・なんとか、これを調べる手立てはないものか?と、ずっと考えていました!
|
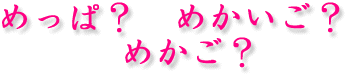
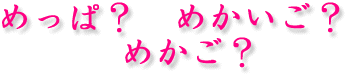
![]()
![]()
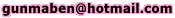 までメールください!待ってます!
までメールください!待ってます!